
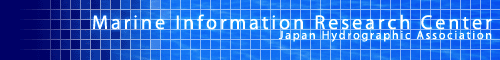

 | サイトマップ |  | English |

 | 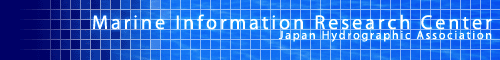 | |||||
 | ||||||
| ||||||
 | ||||||
| トップ >海の知識 >海流の知識 | ||||||
海流の知識
1. 水は高きより低きに流れない1-1. 川の流れの仕組み海流のことを話す前に、「水は高きより低きに流れる」というわれわれの常識について考察しておこう。 ちょっと面倒な議論であるが、中学校で物理学の講義を受けた人なら、誰もが習った筈のことがらだけを基にしているので我慢して欲しい。過去に講義や講演で、なぜそうなのかの説明を聴衆に尋ねてみたことが何度もあるが、未だかって正確な答えが得られた試しがないのはどうしたことなのだろうか。 川の水が川上から川下に向かって流れていることを知らない人は先ずいないが、その理由として通常返ってくる答えは、川の水には重力が下向きに働いているが、それを支える川底の抗力が、傾いている川底に直角方向であるため、川下に向かう重力成分が残ると云うものである。 あるいは、川面が傾いているため、同じ水平面でみるとその上にある水の高さが大きい川上側の方が水圧が高く、川下に向かう圧力傾度(力)があるからという答えもよくある。 しかし、この「川下の方向に力が働いている」ということは、直ちには「川が川下に流れる」ことに結びつかないのである。
ニュートンの運動法則によると、慣性系において「動いている物体に力が働かなければ、その物体は直線等速運動(静止も等速)をする」のであるから、力と速度の間には何等の関係もないということになる。力は速度を変える働きをするもので、加速度と
という関係で、結びついているのである。 従って、「川下の方向に力が働いている」ならば、川下に向かう流れは時間と共にどんどん速くなる筈のものであるし、「川の水は川上から川下に向かうにつれ速度を増していき、谷川の流れは極めて遅いが、川が海に流れ込む所での流速はものすごく大きくなる」筈なのである。 しかし、現実にはそんなことは起こっていない。 大雨が降れば増水して流れが速くなるけれど、普通はある場所でしばらく眺めた位では川の速さはほぼ一定であるし、谷川の流れは速く河口付近の流れはゆるやかである。 すなわち、川の流れほとんど変化せず定常状態にあるのであり、河床の勾配が大きい所ほど速く流れている。 定常状態にあることは、運動の法則からそこに働いている力の合力が0であることを意味する。 従って、「川下の方向に働いている力」は他の力で打ち消されていなければならない。 実際の川でこの働きをしている力は、川岸や川底によって流れている川の水に働く摩擦力である。 川の流れにおける力のバランスを模式的に示したのが図1の上の図である。 いずれにせよ、まず理解して欲しいのは川の水に働く力の合力が0だということである。
それでは何故川の水は川下へ流れるのだろうか。
われわれが通常観察する川の流れのような比較的小規模の流れでは、摩擦力の大きさは流れの速さの2乗に比例し、その方向は流れを妨げる方向に働く。
すなわち、
であり、これが圧力傾度とバランスしているから、 の関係が成り立っている筈である。 川底あるいは水面勾配の大きい山地の谷川では、圧力勾配が大きい。 従って、流れの速度がそれに見合うだけ大きくならないとバランスが保てないし、水面勾配の小さな河口付近では流れの速度は小さくなければならないのである。 「川下の方向に力が働いているから、その方向に流れる」というわれわれの直感は、「高速で動く車の方が、低速で動く車より多量のエネルギーの供給を必要とする」という直感と同様に、暗黙の内に「摩擦力」の存在を仮定したもので、真の「物理学的直感」とはかけはなれたものなのである。 1-2. 海流の仕組み黒潮の幅は100-200kmであり、厚さも数百mを超す。 また、流れは陸岸から離れているし、海底近くの流れは弱い。 このような大規模の流れに働く摩擦力は相対的に非常に小さく、おおまかな力学的なバランスを考えるときは、無視してよい程度の大きさしかもたない。 しかし、海面は一般に平らではなく、海洋のいたる所で圧力の水平勾配が存在している。 海流は後に述べるように変動性に富んでいるが、黒潮が有史以前から流れ続けているように、これもおおまかに云えば、定常状態にあるわけであって、そこに働いている力の合力はほぼ0でなければならない。 そこで登場するのが、自転する地球上の大規模流体運動に、大きな影響を持つコリオリの力(転向力)である。 コリオリの力の働く原理はここでは省略するが、あたかも地球が止まっているかのように考え、運動を地面に相対的に記述した場合(誰もがそのようにしている!)に、考慮に入れなければならない見かけ上の力である。 コリオリの力の大きさは、動いている物体の速度に比例し、その方向は北半球では運動の方向に直角右向きに働く(南半球では直角左向き)。 海流の特性を論じる場合に、コリオリの力の働き方が緯度によって異なり、赤道付近では働かず、その働きは北極で最大になる(緯度の正弦に比例)ことが重要となるが、このことはここでは省略する。さて、海流の力学バランスにおいては、摩擦力がほとんど無視できるから、水面の傾きによる水平圧力傾度に釣り合うのはコリオリの力でなければならない。 図1の下の図でその有様を示すが、水平圧力傾度は当然水面の高い方から低い方へ向かうから、それに釣り合うコリオリの力は水面の低い方から高い方へ向かわざるを得ない。 コリオリの力は運動に直角右向きに働くのであるから、運動は等高線に沿って、水面の高い方を右に見て流れざるをえないのである。 すなわち、海流では「水は高きより低きに流れる」という常識は通用しないことになる。 1-3. 地衡流のバランスもっとも、こんな面倒な議論をしなくても、北太平洋の亜熱帯域に、北赤道海流・黒潮・北太平洋海流・カリフォルニア海流・北赤道海流とぐるっと回った大きな循環があることを考えても、当然すぐ出る結論かもしれない。 ぐるっと回る流れが高きから低きへと流れていたら、一体どこが一番高いのだろうか。不思議なことに、台風等、低気圧の周りを風が反時計回りに吹いていることは誰もが知っている。 この場合も摩擦力が効いてくる地上付近では、低圧部に吹き込む風の成分が見られるが、少し上空では風はほぼ等圧線に沿って高圧部を右に見て吹いている。 海流は決して川の流れに似たものではなく、海の中を吹いている風と考えるべき性質を持っている。 図1下に示したような、水平圧力傾度(大気の場合は水平気圧傾度)とコリオリの力がバランスしているような流れを地衡流(大気では地衡風)と呼んでおり、自転する地球上の大規模流体運動の殆どが、基本的にはこの地衡流のバランスの下にあるこを頭に入れておいて欲しい。 さらに注意しておきたいのは、地衡流というのはそこに働く力のバランスを云っているので、決して原因結果を云っているのではない。 定常的な流れがあれば、それに応じて海面の凹凸があるし、海面に凹凸があればそれに応じた流れの場が存在しているのである。 先に述べた黒潮を含む北太平洋亜熱帯循環は、太平洋の真ん中の水位が周りより高く、そこに大きな高圧部を作っているからで、循環は地衡流のバランスの下でその周りを時計周りに回っているだけのことである。 黒潮も当然水位の高い方を右に見て流れるわけであるから、沖側の水位の方が岸側の水位より高く、その水位差は約1mに達する。 このことは意外に知られていないようであるので、拙著「海流の物理」の中に描いてもらった漫画を図2に示しておく。 最近、人工衛星から表面海流の測定が行なわれるようになってきているが、これは衛星から海水面の高度分布を計測し、地衡流の関係から表面流速分布を求めようとするものである。 測定精度そのものは数cm以下になっているが、測定の基準面であるジェオイドの決定精度が十分でなく、変動成分を中心に検討されているのが実状である。 2. 風によって起こされる水の動きは風の方向とは一致しないし、摩擦力は運動を妨げる方向に働くとは限らない風によって直接起こされる海面近くの流れの方向が風向と一致しないことが示されたのは、フラム号を用いたナンセンの有名な北極探検の際である。 漂流物から北極海を横切る流れのあることを類推したナンセンは、氷に閉じこめられた際に氷上に浮き上がるよう工夫された丈夫な卵型の船底をもった船を作り、氷とともに漂流して北極点に達することを計画した。 1893年9月から1896年8月まで約3年間の氷に閉ざされた生活を送った訳であるが、漂流路は若干北極点からずれたが、ナンセンは当時(1895)としての最高緯度到達の記録を樹立している。 この探検には多くの海洋学者が同行しているが、ナンセンは氷の流される方向が常に風向から右にずれることを観測から示し、帰国後それを説明する理論を学会に求めた。 これに応じて風によって起こされる海洋表層の流れの理論を提出したのがエクマンで、現在でも風によって直接起こされる流れをエクマンの吹送流と呼んでいる。 エクマンは種々の水深の下での流れや、吹き始めの段階での流れの変化の様子等も求めているが、ここでは深い海で、広範囲を長時間にわたって一様な風が吹き続いた場合の結果だけを図3上に示しておく。この図で分かるように、風によって直接起こされる流れの方向は、表面においても風向に一致せず、北半球では風向に対して45度右にずれる。 流れは深さに従って大きさを減ずるが、流向もさらに右へ右へとずれて行き、そのベクトルの先端はら旋を描く。 このら旋を一般にエクマンのら旋と呼んでいる。 面白いのは、流れを鉛直に積分してやって、全体として水はどの方向に流されるかを計算すると、流れの風向成分は完全に打ち消しあって0となり、全体としては水は風向に直角右向きに運ばれることが示されるのである。 北太平洋海流の上には東向きに吹く偏西風、北赤道海流の上には西向きに吹く貿易風が存在するが、これらの風は直接その下の海流を起こし得ない。 エクマンの理論によれば、偏西風は海水を南に運び、貿易風は海水を北へ運ぶことになる。 亜熱帯循環について、その中央の水位が回りより高いことを先に述べたが、二つの風系はこの水位の高まりを起こし、維持する働きをしているのである。 また、カリフォルニアやペルー沖の好漁場を形成する要因となる沿岸湧昇や、赤道湧昇に大きく働いているのが、この「水は全体として風向に直角右向き(南半球では直角左向き)に運ばれる」という事実なのである。 エクマンの理論で海水に働く力は、海面での風の応力と、水中ではコリオリの力と摩擦力である。 この場合は海面近くの現象で摩擦力が重要となるが、摩擦は海面に働く風の応力の影響を海面下に伝える働きをしている。 ここで注目すべきことは、流向が深さと共に変わることから分かるように、摩擦力は流れの方向に逆には働いていない。 エクマンの理論は、ほぼ同様の形で接地層の風速分布にも適用でき、風は上空の地衡風から、地上の風速0までやはりら旋を描いて減少することが示される(図3下)。 しかし、摩擦層の上部で摩擦が効き始めた部分で、上層の地衡風より速い風速が生じる。 すなわち、「自転する地球上では、摩擦力は運動を妨げる方向に働くとは限らない」し、場合によっては「加速する」場合さえあるのである。 もちろん、地球上に置かれていても洗面器の水に息を吹きかければ、水は吹かれた方向に移動する。 エクマンの理論でも、吹き始めは水が風向に運ばれることを示されており、図3のような状態は風が1日程度(正確には1振子日)吹き続けた場合に起こるのである。 われわれの直感は、われわれが息を1日あるいは半日吹きかけ続けることが出来ないという体験に基づいていることを記憶する必要がある。 3. 暖流は決して周りより暖かい海水の流れではない3-1. 暖流の流れ方試みに国語辞典の類を数種類調べてみて驚いたのは、「暖流」という言葉にたいして、例外なく「暖流とは、周りより暖かい海水の流れである」という意味の説明がされていることである。 これは、「暖流」という言葉自体が与える印象が、いかにわれわれの「常識」を狂わせているかを示すものと云える。 現在、海洋物理学分野においては、若干の例外を除き暖流・寒流という用語を使わないのは、この言葉の持つ語感が、背後の物理現象の理解を妨げているからである。図4に、本州南方での黒潮域周辺の海面の凹凸の分布と200m水深における水温分布との一例を示す。 海面の凹凸は地衡流のバランスから表面海流に結びついており、等高線はそのまま海流の流線と考えてよい。 注意していただきたいのは、図4で200m水深での等温線分布がほぼ海面の凹凸分布に対応していることである。 ごく表面の水温分布(例えば人工衛星から測られた水温分布)を除くと、100m水深でも300m水深でもよいのであるが、日本近海の黒潮周辺域では、経験からこの200m水深の水温分布が一番表層の海流分布に似ていることが分かっている。 そこでこの200m水深の水温分布が黒潮の流軸の位置を決めるために広く使われているのである。 海水の密度は、水温と塩分(と水圧)で決まるが、海域を選ぶと水温と塩分の間にある決まった関係が見出されるから、大まかには水温が密度を決めていると考えることができる。 もし、かなり深い水深(例えば1000m)で海流が無いか、あっても非常に弱いとすると、地衡流のバランスから、その深さでの等圧面は水平となり凹凸がない。 すなわち、この面から上にある水柱の重さはどこでも一定であるはずである。 言い替えれば、この面から上層に軽い水すなわち比較的暖かい水があればそこの水柱はより高く、重い水すなわち比較的冷たい水があればそこの水柱はより低くなる。 従って、海面の凹凸の分布とその下の海水温の分布は互いに似たものとならざるを得ないのである。 だから、「暖流は周りより暖かい水の流れではなく、例えば暖流とされる黒潮のような海流は、暖かい水と冷たい水の境目を、ほぼ等温線に沿って、暖かい方を右にみて流れている」ことになる。 3-2. 海面水温の分布と海流物理学的には「海流はほぼ等温線に沿って流れる」のが常識なのであるが、人工衛星からの熱赤外画像に示される海面水温分布を見ると、しばしば黒潮の流域がその両側の海域よりも暖かく、あたかも黒潮は「周りより暖かい海水の流れ」のように見える場合がある。 話はやや複雑になるが、このような衛星画像が一般の新聞紙上に現われることも多いようなので、ここで少し説明しておこう。先に述べたように、表面海流に対応するのは正確には、ほとんど流れがない深い基準面から上の水温(密度)の積分したものであるから、ある深さの水温分布と海流分布が似ていなくても物理学的には何の不思議もないわけである。 しかも、表面水温には海流とは関係しない種々の変動要因があり、激しく変動しているために「表面水温」の持つ海洋物理学的意味は、「海流」そのものよりも理解することが困難である。 従来、海洋学で扱われてきた表面水温は、観測船から紐のついたバケツで組み上げられた海水の温度であった。 この水温はいわば表層数十cmの平均的な水温であり、本当の意味での表面水温ではない。 また、多くの商船・漁船から報告される表面水温が種々の解析に用いられているが、この多くはエンジンの冷却水として汲み上げられた海水の温度で、船の大きさにより吸入口の深さに応じて代表する水深が異なっている。 一方で、人工衛星によって測られている表面水温は、mmといった非常に薄い極表面層の温度であって、日射の強い夏期では、極表面に作られた薄い暖水の層の水温を現わすに過ぎないし、このような水温は著しい日周変化を示す。 このため、風が強く海面が波立っているためや、表面の冷却による対流が起こっているために、極表面層が混合によって壊されている冬期の方が、衛星によって測られた水温分布が、海流などのその下の海洋構造と結びつけて解釈し易いのである。 しかし、表面混合層が発達する冬期でも、表面水温分布と海流場の関係を見る場合 にも次の3つの可能性を頭においておかねばならない。
3-3. 「暖流」という言葉の物理学的説明海洋物理学の立場では、「暖流」「寒流」という言葉は以上のように誤解を招く恐れがあるので通常は用いない。 ただし、対馬暖流・津軽暖流・宗谷暖流のようにその流れの右側すぐに陸岸がある場合には、便宜的に使用されてはいる。これは、黒潮の場合、流れの右に暖水があるわけであるが、流れの沖側の境界は明確でなく暖水は亜熱帯太平洋の中央部の水につながっているため、「強流域」と「暖水域」の対応がつかないのに対し、上記の3つの海流は「暖水域の右端」が岸そのものであると共に、流れも岸のすぐ近くまで流れているから、結果的に「強流域」即「暖水域」となっているからである。 しかし、私などは論旨を一貫させるため、対馬海流・津軽海流という呼び方に固執している。しかし、海洋物理学者がわめきたてた所で、「暖流・寒流」という言葉が使用されなくなるとは思えない。 「すぐ側を暖流である黒潮が流れる紀州や伊豆・房総は暖かい」というセリフは、観光案内のパンフレットに満ち溢れているし、同じ学者でも地理学分野ではこの便利な言葉を使い続けるに違いないのである。 ある海洋物理学者はかつて、「海流の中で高緯度に向かって流れる海流を暖流と呼び、低緯度に向かって流れる海流を寒流と呼ぶ」という新しい定義を定着させようと提案したことがあるが、残念ながら津軽暖流のような例外があるし、この定義もいたって「地理学的」であって「物理学的」とは言い難い。 いささか面倒ではあるが、ここまで話してきた限り、正確な「物理学的」定義を試みておこう。 さて、「黒潮の洗う紀州は暖かい」という言葉は間違ってはいない訳で、「だから黒潮は周りより暖かい水の流れである」という具合いに飛躍させる所に問題があるのである。 紀州が温暖であるのは、物理学的に正確に述べれば、「黒潮が暖かい」からではなく、「黒潮がその上の大気に熱を与えているから」である。 このことは黒潮の表面水温がその上の気温より暖かいことが必須条件ではあるが、前節の3で述べたように、止まっていれば大気温とある種の平衡条件を取り得るから、高温の水がどんどん運ばれて来ることも大きく働く。 少なくとも、物理的に「黒潮の水が周りより暖かい」必然性はどこにもないことを理解して欲しい。 従って物理的に定義するならば、「暖流とは、その上の大気に熱を与え、それ自身は流れの方向に徐々に冷えていく海水の流れ」を指す言葉であり、寒流も同様に大気から熱を奪いながら流れる海流と定義することが出来る。 しかし、この冷え方はゆるやかで黒潮の水が紀州沖から三陸沖に達するまでの間に流軸の水温が1-2度低下する程度でしかなく、先に述べた「海流はほぼ等温線に沿って流れる」という関係を目に見えるほどには変えるものではない。 従って、「暖流の洗う紀州が暖かい」ということは何等間違っていないのではあるが、出来ればここで述べた事情を頭の片隅に置いていただきたいものである。 4. 海水は必ずしも海流とともに運ばれるとは限らない海水が海流とともに運ばれないというと、何を言い出したのだろうと不思議そうな顔をされる人が多い。 もちろん、流れて行くうちに、海流の中の水は周りの水と混じり合うから、海流の中の水が何時までも海流の中に留まるとは限らない。 しかし、ここでお話したいのは、もう少し直接的な事柄である。例えば、図5に示した仮想的な流線分布を見ていただきたい。 流れは全体として図の下から上方へゆるやかに流れているが、中央の部分で右向きに流線が折れ曲がり、その間隔も非常に狭くなっている。 すなわち、この部分ではほぼ右向きの強い流れが存在している。 もしこのような状態が実際に海の中に実現していて、観測船を出して流れを観測したらどうなるであろうか。 中央の部分を除く上下の部分では流れは弱く、われわれはそこには海流は無かったと報告するであろう。 しかし、中央部には左から右に向かう強い海流が存在していたと報告するに違いない。 言い替えれば、図の中央部を右から左に向かう海流が観測されることになる。 そうして、海水は明らかに海流と共には運ばれていないのである。 実際の海で図5に示されたような極端な海流が存在することは先ずないであろうが、この例はわれわれが「観測する」海流が正確には水の流れを示しているとは限らないことを説明している。 物理的な用語でいうならば、大規模な海流においてわれわれが観測しているのは、「流れの速い場所」という「位相」が空間的につながっている帯状の部分を「海流」と呼んでいることになる。 海の波を眺めるとき、われわれは水の盛り上がった部分(位相)、すなわち波の峰、が動いて行くのに注目するが、これは水の動きとは別物であることは誰もが知っていよう。 実際の現象を正確に理解するためには、観測されたものが「実質の流れ」なのか「位相の動き(あるいはつながり)であるかを十分に理解しておく必要があるのである。 これとは少し違うが、「海流は川の流れに似たものだ」と誤解している人が少なくない。 前にも述べたように、地衡流である海流は「川の流れ」よりは「風」に似た性質をもっている。 日本海を流れる対馬海流の水は、黒潮系の水の影響を非常に受けた水である。 そのためか、対馬海流は九州南西で生じた黒潮の支流がそのまま対馬海峡を通って日本海に入ったものと思いこんでいる人が非常に多く図6の上のような海流図がしばしば解説書に現われる。 しかし、九州の西部で通常観測されるのは南下流で、東シナ海を対馬海峡に向かって流れるような顕著な海流は観測されたためしがない。 わたしはかならず図6の下に示したような正しい海流図を描くように主張し続けているが、海流は川の流れのように一つながりのものという誤った常識があり、なかなか改めてもらえないのが現状である。 人は「風」をそのような概念で捉えることがないのに、なぜ海流になるとそう思い込むのか不思議である。 実際には東シナ海の黒潮の沿岸寄りに、黒潮系水と沿岸系水の混ざった海水の大きなプールが存在していて、そこの溜り水が日本海に流れ込んでいると考えるべきなのである。 ちょっと不思議なのは、一般の人が、むしろ川の流れに対しては、このような現象をよく理解されていることである。 例えば琵琶湖には沢山の川が流れ込んでいて、この川の流れはかなりの速さを持っている。 一方琵琶湖の水は瀬田川として流れ出すが、もちろんそこでの流れは速い。 しかし、琵琶湖の中に流れ込む川の水が瀬田川のほうにどう流れて行くかについては、殆ど興味を持つ人はいない。 広い海で当然同様のことが起こっている筈で、あちこちに淀みがあって海流がそこで消えても何の不思議もないのである。 海洋を正しく理解するためには、われわれの「誤った常識」から逃れることがどうしても必要である。 海流を「流れが速い」という「位相」がつながった帯と考えることで、誤解の一つを解消できればと図5のような図をあえてお示ししたわけである。 5. 海流は風のように(風の中の羽のように)変動性に富む海流が変動性に富むことは、人工衛星の熱赤外写像を見る機会が増えているので、実感として感じることが出来る人も多いかと思う。 黒潮続流域で黒潮のフロントの微細構造の観測をした時、海洋速報で示されていた黒潮流軸の位置まで船をもっていっても強い流れがなく、やむを得ずさらに40km以上南下してやっと強流域を見付け得たことがある。 そこから北上しながら精密な観測を行なったのであるが、驚いたのは海洋速報での流軸位置まで戻ったところ、僅か数時間後であるのに流軸位置は変化しており、そこは正に黒潮流軸であることを示す強い流れが見出されたことである。 このような短周期の変動はしばしば観測されるし、空間的にも強流帯の中に特に流れの強い部分がフィラメント状に多数存在することも報告されている。 このような現象は、海流が正に大気中の風と同じ性質を持つと考えれば容易に理解されよう。図7に約10年間に観測された黒潮流軸の位置を全部1枚の図に描いたものを示す。 これを見ても黒潮の流れが如何に変動性に富むかが分かろう。 さらに図8に湾流周辺の海況の模式図を示しておくが、大洋中には無数の種々の渦が存在し、それが複雑に移動し、消散を繰り返しているのである。 重要なのは、大気中の低気圧・台風のような渦の直径が2000km程度の大きさであるのに対し、海洋中の渦は100km程度と1桁以上小さいことである。 ここでは深入りしないが、台風をちゃんと表わせないような粗いメッシュ間隔での数値シミュレーションで天気予報をしても意味がないように、気候変動の予測に関連した海洋の数値シミュレーションでは、この海洋中の渦をちゃんと再現できなければ役に立たないことが示されている。 しかし、渦の大きさが1桁小さいとするとメッシュの間隔も1桁小さくしなければならない。 現象は3次元的であり、これに時間間隔も小さく取るとすると、おおまかに言って同じような計算をするのに、海洋の計算は大気の計算の一万倍の手間・時間が必要になる。 また計算に用いるデータも大気に比べてずっと限られている。 このため1980年当時の計算機では事実上世界の海洋全体の十分なシミュレーションは不可能である。 これを可能とするような計算機の出現を紀元2000年と予測し、その時までに気候問題に結びついた海洋の数値実験を行なうための準備としておこうと計画されたのがWOCEという1990年から開始された国際共同研究で、現在ほぼ終了期を迎えている。 海洋の基礎研究と水産の問題を結びつけるためにも、海洋の変動性と渦の問題は無視することができない。 今後のより科学的な水産学を目指す場合、このことは非常に重要な問題であることを記憶しておいて欲しい。 6. 水は放っておくと、ほとんど混じり合わない違った水塊が隣あって存在しても、放置しておくと殆ど混じりあわないものであるが、水は混じり合い易いという誤解も、驚くほど一般的にあるようである。 水は放っておいてもすぐ混ざると思う方は、コーヒに砂糖を入れたときに、スプーンでかき混ぜないで飲んでみられるとよい。 カップの上半分はコーヒが完全に冷めてしまうまで待っても、殆ど甘味がないことに気付く筈である。 あるいは風呂を沸かせて、これもかき混ぜずに風呂の水の温度が一様になるのを待って見るといい。 上下の温度差は明確なままに、水の温度は時間とともに下がって行ってしまうだろう。 コーヒ・カップや風呂桶のような小規模現象でさえこうなのであるから、海洋の大規模現象ではたいていの場合、「水はほとんど混じり合わない」と考えなければならないのである。海洋を物理的に扱う場合、第1近似としては水温や塩分は保存量と考えるのは、「水が殆ど混じり合わない」ためなのである。 海流は地衡流のバランスにあることは先に論じたが、表面近くを除くと海流はほぼ等温線に沿って流れていることを述べた。 水温や塩分が保存量であるならば、流線に沿って水温・塩分に変化は起きない筈である。 「水が混じり合わない」ことが地衡流が安定して存在することの大きな原因の一つと云うことも出来るのであろう。 海洋学において、TS図上に観測値をプロットして水塊の性質を研究・議論することが広く行われていることは周知のことであろう。 世界の水塊の性質がTS図上で、それぞれ特徴的な曲線として現れ、これを用いた分類がされているが、最近では溶存酸素や栄養塩その他の量を組み合わせた水塊分析が行われるようになっている。 もちろん、海水は完全に混じり合わないわけではない。 海洋フロント付近では、接する二つの水塊の中間の性質をもった水が存在しており、TS図の上で混ざり具合いを論ずることも広く行われている。 水塊の混合や水塊の変質過程が現在の海洋物理学において重視され、盛んに研究されているが、それは言い替えると、「第一次近似では水は混ざらない」という前提から出発して、第二近似・第三近似に進んで行こうとしているのである。 7. 地球上の大規模流体運動の理解には、「流れ」よりも「渦度」を考える方が簡単である長くなったし、この問題はやや専門的になるので、ここでは詳しい説明は割愛する。 流体の基礎方程式を渦度方程式に変換してやると、いくつかの項が消えてくれるという利点があるのであるが、それに加え地球の自転効果のコリオリの力やその緯度変化の項(ベータ項)が、単純な形で直接的に表現できるからである。 より高度な海洋物理学を学ばれる場合には、是非この「渦度」を直感的に捉える訓練をされることをお勧めする。 このページの最初に戻る |
| [前のページに戻る] |
|
Copyright(C) Marine Information Research Center, Japan Hydrographic Association. All Rights Reserved. |
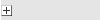 |
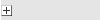 |
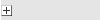 |
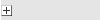 |
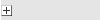 |
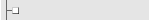 |
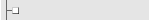 |  |
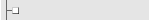 |
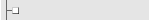 |
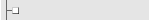 |
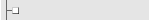 |
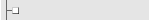 |
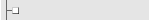 |
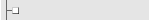 |  |
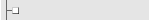 |
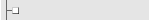 |
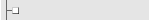 |
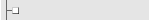 |
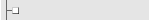 |
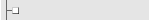 |  |
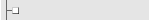 |
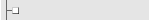 |  |